医療現場に必要なメンタルヘルス対策は? 不調の原因や影響も併せて解説
2025/7/9
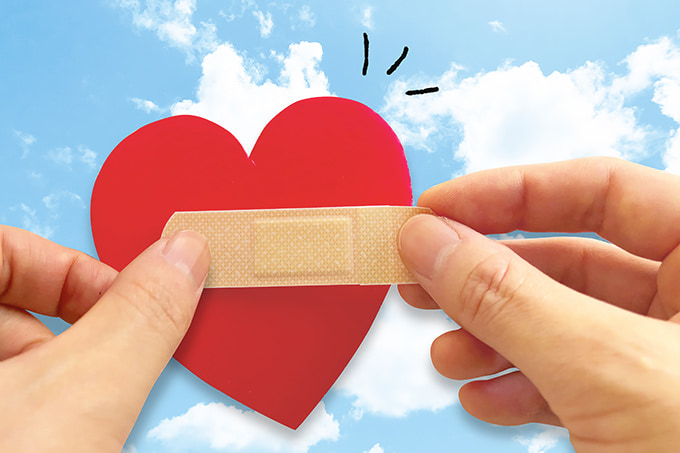
近年、医療従事者のメンタルヘルス不調が深刻な社会課題となっている。医療従事者は、人命を預かる責任のもと、過酷な労働環境で働き、人手不足や長時間労働、複雑な対人関係など、多くの要因でストレスを抱えている。
これらの負荷が積み重なることで、心身に不調をきたし、離職や業務の質の低下といった悪影響を及ぼすことも少なくない。本記事では、医療現場におけるメンタルヘルス不調の原因や影響、そして具体的な対策について解説する。
(1)医療現場のメンタルヘルス不調の原因
現代の医療現場において、看護師をはじめとする医療従事者のメンタルヘルス不調は深刻な問題となっている。特に人手不足や長時間労働といった労働環境に加え、対人関係や患者対応に起因するストレスは大きい。ここでは、医療現場におけるメンタルヘルス不調の主な要因について解説する。
・人手不足
医療現場では慢性的な人手不足が続いており、看護師一人あたりの業務負担が増えてストレスを感じやすい状況になっている。看護師の総数は増加傾向にあるものの、高齢者の増加に伴う医療ニーズの急増に追いついていない。
日本の100床あたりの看護師数は、諸外国と比較して著しく少なく、平均でおよそ4分の1にとどまっているとのデータも存在する。これにより、看護師一人が受け持つ患者数が多くなり、日々の業務負担は過剰になる。特に夜勤帯では人員がさらに減るため、肉体的にも精神的にも大きなストレスを感じる要因になっている。
・長時間労働
看護師の勤務形態は非常に不規則であり、前残業や後残業が常態化しており、長時間労働によるストレスが深刻である。緊急対応やイレギュラーな業務が日常的に発生することにより、業務時間の調整が困難であり、結果として長時間労働が避けられない状況にある。こうした労働環境が継続すれば、心身の疲労は蓄積され、メンタルヘルス不調のリスクが高まるのは必然である。
・職場内の関係
医療現場では、チーム内の連携や意見の食い違いが、ストレスの原因になる。医療現場で働く上では、医師や看護師、薬剤師、他科のスタッフなどと密接に連携を取る必要があるが、それぞれの立場や経験年数、価値観の違いが摩擦を生むことも少なくない。
意見の食い違いや、職種間での意思疎通の難しさは、精神的な緊張状態を引き起こしやすい。職場内のコミュニケーションに多くの時間とエネルギーを割かれる医療従事者は、それだけ精神的負荷も大きくなっていると言える。
・上司との関係
医療現場において、上下関係の厳しさやパワーハラスメントが、若手看護師のストレス要因になっている。先輩よりも早く退勤できない、休みが取りづらいなどのケースが多い。
さらに、看護職員の労働実態調査では、上司からのパワーハラスメントが最も多いという結果が報告されており、20歳未満で85.7%、20~24歳で78.7%、25~29歳では70.7%と、若手層の多くがその被害を訴えている。厳しい指導は患者の安全を守るために必要であるとはいえ、指導とハラスメントの境界があいまいなままでは、若手の心身を追い詰めることになるだろう。
・患者とのコミュニケーション
患者対応の中でのトラブルや葛藤も、看護師にとって精神的な負担となっている。忙しさのあまり患者に十分な対応ができないことへの罪悪感や、患者・家族からの理不尽な言動への対応など、感情労働としての側面が色濃く表れている。
また、患者とその家族間のトラブルに巻き込まれるケースもあり、これがさらに精神的な負担を大きくする要因になる。患者との関係は看護師のやりがいの源でもあるが、同時に過度なストレスの源でもある。
(2)メンタルヘルス不調が医療現場に与える影響
医療従事者のメンタルヘルス不調は、個人の問題にとどまらず、職場全体の機能に深刻な影響を及ぼすものである。高ストレス環境にある医療現場では、心の不調によってパフォーマンスが低下し、離職やトラブルを引き起こすケースも少なくない。
ここでは、メンタルヘルス不調が医療現場に与える具体的な悪影響について解説する。
・医療従事者の離職を招く
近年、心の不調による退職が増え、職場全体に悪影響を及ぼしている。うつ病や不安障害、心身症などのメンタルヘルス不調を理由に欠勤や長期休職、さらには退職に至る医療従事者が年々増加している。
そして、一度休職すると復職のハードルが高くなり、再び退職してしまうケースも多く見られる。このような離職者の増加は、残されたスタッフにさらなる負担を強いる結果となり、職場の雰囲気や業務体制にも悪影響を及ぼす。
人員が欠けることで新たなストレスが生まれ、悪循環に陥るリスクが高まるのだ。
・業務効率やパフォーマンスが低下する
メンタルヘルスの不調は、単に心の問題にとどまらず、身体的な不調とも密接に関連し、意欲と生産性を大きく下げる原因にもなり得る。強いストレスを受け続けることで集中力や判断力が低下し、日々の業務にも影響を及ぼすようになる。
医療の現場では一つのミスが重大な結果を招くこともあるため、意欲やパフォーマンスの低下は深刻な問題だと言える。業務効率の低下が進めば、患者への対応にも支障をきたし、現場全体の質の低下を招くことになるだろう。
・トラブルにより病院のイメージが落ちる可能性がある
メンタルヘルス不調が深刻化すれば、病院の信頼とブランドに大きな打撃を与えかねない。例えば、院内での自殺や重大な医療事故が報道された場合、病院のイメージダウンは避けられず、患者離れなどの問題を招く恐れがある。
また、内部のストレス環境が表面化することで、働く場としての魅力も失われ、優秀な人材の確保が困難になる。メンタルヘルスケアの不足が経営リスクに直結することを、組織として強く認識する必要がある。
(3)医療現場のメンタルヘルス対策
メンタルヘルス不調による離職や業務効率の低下を防ぐためには、医療現場における対策が欠かせない。医療従事者が心身ともに健やかに働き続けるためには、予防と早期発見、そして職場全体で支え合う仕組みが求められる。
ここでは、実際に取り入れられる具体的なメンタルヘルス対策を紹介する。
・メンタルヘルスに焦点をあてたカンファレンスの実施
医療現場では、スタッフが心の健康に向き合うための学びの場を定期的に提供することが重要である。カンファレンスや勉強会を開催し、職員全体でストレスや心の健康について考える時間を確保することは、有効な手段の一つであろう。
全員でのストレスチェック実施や、eラーニングで学ぶなどの方法も効果的だ。厚生労働省の「こころの耳」では、オンラインでストレスチェックを行えるツールや動画コンテンツが公開されており、院内教育に活用しやすい環境が整っている。
・一定期間ごとの面談を実施
スタッフの不安や悩みに気づくための対話の機会として、定期的に面談することも有効である。特に、新人職員や管理職、家庭の事情を抱えるスタッフは、ストレスをため込みやすい傾向にあるため、対話の機会を設けることが不可欠である。
また、「遅刻や欠勤が続く」「ミスが増える」などの変化が見られる場合には、すぐに声をかけるなどの対応が求められる。
・医療従事者の意見を取り入れた環境整備
職場環境を改善するためには、現場の声を丁寧に拾い上げ、その声を反映した職場づくりを行い、安心と信頼の風土を育むことが重要である。管理者が日頃からスタッフとコミュニケーションを取り、職場の課題を共有しながら改善に取り組めば、安心感が増し、信頼関係が構築されるだろう。
「自分の声が届いている」という実感は、働きやすさにも直結し、結果としてメンタルヘルスの安定にも寄与する。
・シフトの見直し
しっかり休めるシフト体制が、ストレス軽減と働きやすさのポイントになる。十分な休息を取ることは、ストレスの軽減に直結する。医療現場では、緊急対応や残業が常態化しており、スタッフが十分に休めない状況が続いているケースが多い。
そこで、管理職はシフト体制の見直しを図る必要がある。例えば、「勤務間インターバルの確保」「休憩時間の徹底」「希望休の取りやすさ」など、休める環境づくりを重視したシフト管理を実施することが求められる。徐々に制度を整えることで、働きやすい職場づくりにつながっていくだろう。
(4)まとめ
医療現場におけるメンタルヘルス不調は、個人の健康問題にとどまらず、職場全体のパフォーマンスや患者へのケアにも影響を与える重要な課題である。人手不足や長時間労働、職場の人間関係といった多様な要因がストレスを引き起こしており、それらを軽視することはできない。
現場で働く職員が安心して業務に取り組めるよう、職場全体での対策と支援体制の整備が不可欠である。医療従事者が健やかに働き続けられる環境づくりが、結果として医療の質を高めることにもつながるだろう。
病院ナレッジリスト
- 【育成担当者向け】病院の人事評価や教育制度を設計する5つのFAQ(2025/10/30)
- 【採用担当者向け】病院の働きやすさや福利厚生を強化する5つのFAQ(2025/10/23)
- 【人事担当者向け】病院の人材確保や離職防止に役立つ5つのFAQ(2025/10/16)
- 【病院経営者向け】病院の人事労務管理を最適化する5つのFAQ(2025/10/9)
- 病院の職員配置基準を解説 医療法施行規則にもとづく最新の人員配置標準について(2025/7/30)
- 看護師の雇用形態の種類を解説! 代表的な働き方のメリット・デメリットも紹介(2025/7/23)
- 医療現場の有休管理を効率化するためには? 現状や課題も併せて解説(2025/7/16)
- 医療現場に必要なメンタルヘルス対策は? 不調の原因や影響も併せて解説(2025/7/9)
- 医療機関の人手不足にどう対応する? 原因・リスク・対策を紹介(2025/7/2)
- 医療スタッフの教育制度を整えよう! 取り組みのポイントや注意点を紹介(2025/6/25)
- 医療機関で取り入れたい福利厚生は? 注目されている理由や代表的な制度を紹介(2025/6/11)
- 病院における人事評価制度の課題や導入のメリットは? 見直しポイントも紹介(2025/6/4)
- 医療現場の労務問題とは? トラブル防止と人手不足解消のための対策も紹介(2025/5/28)
- 看護師の離職率は高い? 離職の理由や対策も紹介(2025/5/21)
- 医療機関における就業規則で確認したい事項 掲載項目や作成方法も紹介(2025/5/14)
- 看護師の勤怠管理における課題とは? 対策や導入システムの選び方も紹介(2025/5/7)
- 病院の労務管理とは? 課題・実務の内容・対策方法などを解説(2025/4/30)
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド

