人材確保につながる製造業の福利厚生とは? 導入のメリットと成功例を解説
2025/9/3
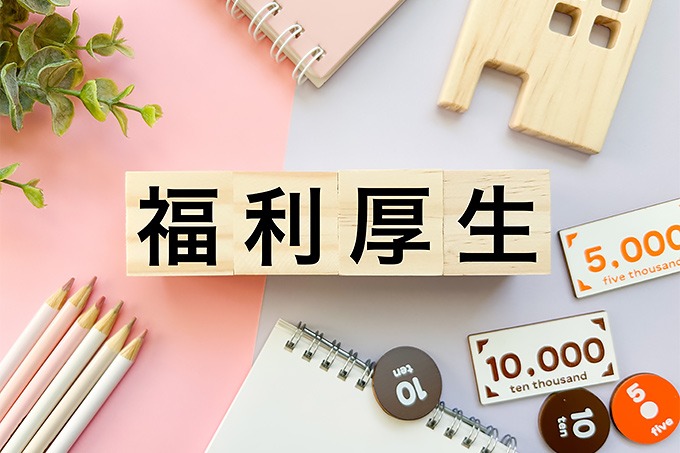
日本の製造業は、深刻な人手不足という構造的な課題に直面している。少子高齢化や若年層の製造業離れにより、安定的な人材確保が難しくなっている中、福利厚生の見直しが注目を集めている。
福利厚生は単なる制度にとどまらず、従業員の満足度や企業の魅力を高める手段として、極めて有効な手段である。本記事では、製造業が福利厚生を導入・充実させるメリットや具体的な成功例を紹介し、人材確保につなげるヒントを提示する。
(1)製造業が抱える人手不足の問題
製造業は、人手不足という問題に直面している。特に少子高齢化の影響により、若年層の就業者数が減少し、将来的な労働力の確保が困難になることも考えられる。このような状況下では、少人数でも生産体制を維持できる仕組みの構築が不可欠である。
また、他業種と比較して高齢者や女性の就業率が低い点も課題である。今後は、高齢者や女性が安心して働ける環境整備が急務であり、多様な人材の確保が製造業の将来を左右する重要なカギになるであろう。
・製造業の労働環境の現状と課題
製造業の現場では、特有の労働環境上の課題を抱えている。騒音・粉じんなどによる健康被害や、重機や危険物の取り扱いに伴うケガなど、さまざまなリスクが懸念される。
さらに、夜勤を含む交替勤務は生活のリズムを乱しやすく、身体的な疲労のみならず、心理的な負担も大きい。これらの要素は、離職率の上昇や人材確保の難航といった悪循環を生み出している。
こうした現状を踏まえ、従業員が安心して働ける職場づくりが課題なのである。作業環境の安全性向上や健康への配慮に加え、メンタルヘルスケアの体制整備など、心身ともに支援する仕組みづくりが求められている。
企業が率先して仕組みづくりに取り組むことが、会社の成長につながるのだ。
・安定的な人材確保の重要性
帝国データバンクが公表している「全国企業倒産集計上半期報」によると、人手不足を原因とする製造業の倒産件数は、2025年上半期に過去3年で最多になった。技術やノウハウの継承、生産性向上、イノベーションの創出などの企業価値の向上にも優秀な人材の力が必要だ。
人材の安定確保は、企業の競争力に直結するものである。優秀な人材を安定的に確保し、定着させるためには、労働環境の改善のみならず、従業員のライフスタイルに寄り添った柔軟な働き方の導入や、福利厚生の充実など、多角的なアプローチが必要なのだ。
(2)製造業における福利厚生とは
福利厚生とは、給与や賞与以外の形で従業員およびその家族に付与される報酬のことである。福利厚生には大きく分けて「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類が存在する。
法定福利厚生は、従業員とその家族の健康維持や生活の安定のため、企業が所定の割合で負担して提供することが義務づけられており、健康保険・介護保険・労災保険などを指す。
一方、法定外福利厚生は、企業が独自に設ける制度であり、住宅手当・通勤手当・退職金制度などが含まれる。
これらは従業員やその家族の生活の質を高めると同時に、企業への定着率を高めたり、モチベーションや生産性の向上を図ったりするために機能する。つまり、従業員が安心して長く働き続けるためには、こうした制度の整備が欠かせないのだ。
(3)製造業が福利厚生を充実させることで得られるメリット
製造業界では人手不足や離職率の高さが大きな課題になっている。そのような中、福利厚生を手厚くすることで、企業にとってさまざまなメリットが生まれる。
そのメリットとしては、人材確保はもちろん、生産性の向上や節税効果、さらには企業ブランドの価値向上にまで及び、福利厚生は単なる従業員へのサービスという枠を超えた経営戦略の一つとして注目されている。
ここからは、製造業が福利厚生を充実させることによって得られるメリットについて解説する。
・人材確保につながる
人手不足状態の製造業においては、特に労働環境への配慮が求められる。従業員にとって、労働環境課題のマイナス面を補完できる魅力的な福利厚生を導入すれば、求職者からの応募の増加も期待できるだろう。
また、新規採用だけでなく、既存の従業員の満足度を高めることにもつながる。結果として、優秀な人材の離職防止や定着率の向上につながるため、安定的な人員確保が可能になる。
・業績アップにつながる
福利厚生が充実している企業では、従業員が安心して業務に専念できる環境が整っている。働きやすい職場環境は、従業員のモチベーションを高めることにつながる。
従業員のモチベーションが上がれば、結果的に作業効率が上がり、一人当たりの生産性が向上する。こうした従業員一人ひとりのパフォーマンスの向上が、企業全体の業績に良い影響をもたらすのである。
・節税につながる
福利厚生にかかる費用のうち、一定の条件を満たす支出は「福利厚生費」として経費に計上できる。これにより、会社としては利益を抑えることが可能になり、結果として法人税の負担軽減につながる。
福利厚生を充実させることは、従業員満足度の向上のみならず、税務上のメリットも享受できるという点で、経営上、極めて合理的な施策だと言える。
・ブランド力の向上につながる
福利厚生の充実による、従業員を大切にする企業のイメージは、人材確保の面だけでなく、取引先をはじめとしたステークホルダーに良い印象を与えるものである。
福利厚生を充実させることは、信頼性の向上や新規市場の開拓など、ビジネスにポジティブな影響を及ぼす要因にもなり得る。結果として、地域において良い評判が広がったり、企業価値を高められたりなど、ブランド力の向上につながるのである。
(4)製造業における福利厚生の成功例
福利厚生の充実は、従業員の働きやすさを高めるだけでなく、人材の確保や企業イメージの向上にも寄与するものである。近年では、製造業においても人手不足への対応として独自の福利厚生を導入する企業が増加している。
以下では、製造業における福利厚生の具体的な成功例を紹介する。
・食事補助
交替勤務や長時間労働などにより、不規則な生活に陥りがちな製造業においては、勤務中の食事を補助する福利厚生は大きな魅力となるものだ。企業の中には社食の無料化に取り組んで人材確保につなげた事例もある。
食事補助は、毎日の生活費負担を軽減できる点で従業員にとって実用的かつ魅力的であり、他社との差別化要因にもなり得るだろう。
・制服手当の支給
制服を廃止し、好きな服装で仕事に臨むための制服手当を毎月支給した事例がある。従業員は自分に合った作業服を選んで仕事に取り組めるため、快適さが増し、結果として従業員のモチベーションアップにつながったと考えられる。
こうした柔軟性は、従業員の自由度を高める制度であり、多様性が注目される現代社会においては、今後ますます必要な視点であろう。
・子育て支援
出産祝い金制度や託児所の設置といった子育て支援を充実させることで、仕事と子育ての両立に力を入れている企業が増えている。女性従業員がライフステージの変化に伴って抱きがちな悩みに寄り添うことで、出産後も働きやすい環境が安心材料となるほか、企業イメージの向上にも大いに寄与するのである。
さらに、子育て支援に力を入れることで、地域社会からの評判も高まり、安定した人材確保につながるなど、好循環が生まれることも期待できる。
製造業ナレッジリスト
- 【労務担当者向け】製造業の長時間労働の課題に取り組むための5つのFAQ(2025/11/20)
- 【人事労務担当者向け】製造業の人材確保の課題を解決できる5つのFAQ(2025/11/13)
- 【労務担当者向け】製造業の勤怠管理の課題を解決できる5つのFAQ(2025/11/6)
- 製造現場で働き方改革を実現するための3つのポイントを紹介!(2025/10/22)
- 製造業で重要視されるコンプライアンスのポイントとは? 4つの対策を解説(2025/10/15)
- 製造業はなぜ残業が多いのか? 労働時間が多くなる理由と対策を紹介(2025/10/8)
- 製造業で深刻化する人材確保問題の原因と解決策を徹底解説!(2025/10/1)
- 製造現場のDXが重要な理由とは? メリットとおすすめツールも紹介(2025/9/24)
- 製造業の就業規則は業種特性を考慮しよう! 就業規則の作成ポイントを解説(2025/9/10)
- 人材確保につながる製造業の福利厚生とは? 導入のメリットと成功例を解説(2025/9/3)
- 製造業でのOJT活用術! 人材育成におけるメリット・デメリットを解説(2025/8/27)
- 製造業の離職率はどのくらい? 離職率が高まる原因や改善方法も解説(2025/8/20)
- 工場の勤怠管理における課題とは? システム導入のメリットや選定方法も紹介(2025/8/6)
大幅に効率化!
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!

