製造業の就業規則は業種特性を考慮しよう! 就業規則の作成ポイントを解説
2025/9/10
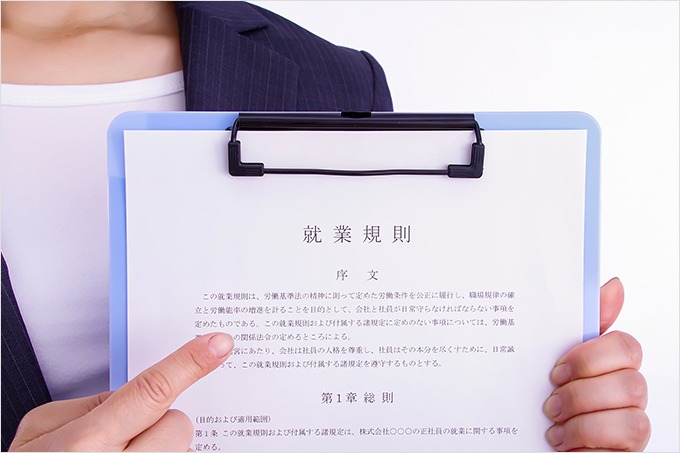
就業規則は、企業運営や労務管理において欠かせない重要な規程である。特に製造業では、交替勤務や安全管理など、業種特有の事情があるため、就業規則の整備は企業の安定した運営にも直結する。
本記事では、就業規則の基本的な概要から法的義務、記載すべき項目、さらに製造業における具体的な作成ポイントやテンプレートの活用法などを解説する。
(1)就業規則とは
就業規則とは、従業員の労働時間や給与など、労働条件および職場内のルールを明文化したものである。製造業のように危険を伴う作業や交替勤務が存在する業種においては、その特性を踏まえた内容にすることが求められる。
労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する事業場に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出を義務づけている。しかし、法的義務がない場合でも、就業規則を整備していないと多くのデメリットが生じる。
例えば、採用時に応募者へ不安を与えて人材確保が難しくなったり、助成金の受給対象外になったりすることが考えられる。また、問題のある従業員に対する懲戒処分が困難になるなど、労働トラブルのリスクも高まり、解決に時間がかかることも考えられる。
このような理由から、企業規模にかかわらず、就業規則を整備することが望ましい。
(2)就業規則を構成する3つの記載事項
就業規則は、企業と労働者との間で適切な労働環境を維持するための基本的なルールを定めたものである。就業規則には記載が義務づけられている事項と、任意で盛り込める事項がある。ここでは、就業規則を構成する3つの記載事項について解説する。
1.絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、すべての企業が必ず就業規則に盛り込まなければならない事項のことである。
労働基準法第89条により、始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇などの「労働時間」、賃金の決定・計算・支払い方法や締切日・支払日などの「賃金」、「昇給」や「退職(解雇事由を含む)」に関する内容は必須事項とされている。
- ※参考:[e-Gov法令検索]労働基準法
2.相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、会社の規則で制度として定めがある場合に、就業規則に記載しなければならない事項のことである。
具体的には、退職手当、賞与、最低賃金額、食費・作業用品の費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰および制裁といった8項目がこれに該当する。
これらは定めがある場合に限って記載が求められるものであるため、企業の方針や特性に応じて記載する。
3.任意的記載事項
任意的記載事項とは、法令に定められた記載事項ではなく、就業規則に記載するかどうかは企業の判断で決められる項目である。
例えば、服務規律や休職制度、副業に関する規定などが挙げられる。これらを記載することで、労働条件や職場でのルールをより明確にし、組織内の秩序を保ちやすくすることができる。
就業規則を作成・見直す際は、これらの内容を含んでいるかを確認し、実情に即した形で作成することが望ましい。
(3)製造業の就業規則を効率的に整備するテンプレート活用法
製造業においては、作業形態や勤務時間、労働安全衛生など、他業種とは異なる特有の事情を反映した就業規則の整備が求められる。
しかし、ゼロから就業規則を作成するには専門知識と時間が必要であり、実務上の負担も大きい。そのため、テンプレートを活用して効率的に整備することをお勧めする。
ここでは、テンプレート活用の利点と注意点、厚生労働省が提供するモデル、そして民間テンプレートの特徴について整理する。
・テンプレートから作成する利点と注意点
テンプレートを用いた就業規則の作成は、手間を省きながら基本的な記載項目を網羅できる点が大きな利点である。特に、作成の手間がかからず、記載事項の抜け漏れを防げる点は、実務上のメリットが大きい。
一方で、テンプレートにはいくつかの注意点も存在する。例えば、テンプレートの内容が最新の労働法規と整合していない可能性がある。また、自社の業務内容や組織文化にそぐわない場合もある。特に、あいまいな文言が含まれていたり、従業員の処遇を重視した内容になっていたりする傾向があり、企業側にとってリスクになる場合がある。
・厚生労働省のモデル就業規則
常時10人以上の従業員をかかえる事業者向けに、厚生労働省が提供している無料テンプレートがある。これは、定期的に法改正に対応して更新されるもので、信頼性はあるものの、汎用的な内容になっているため、それぞれの業種特性はあまり考慮されていない。
そのため、モデル就業規則を利用する場合には、業種や企業の実情に応じてカスタマイズする必要があるだろう。
・民間テンプレート
民間のテンプレートには、無料版、有料版が存在する。無料版のテンプレートは汎用的な項目を網羅しているが、法改正対応のスピードや精度が有料版に劣る。
一方、有料版は、法改正対応のほか、特定業種向けのカスタマイズに優れているため、製造業の特性を踏まえた内容にアレンジすることも可能である。専門家によるサポートが受けられる場合もあり、特性に応じた就業規則を作成するにあたっては、大きな支えになるはずだ。
安全管理が重視される製造業の就業規則を整備するには、信頼性の高さや実用性、そしてサポート内容など、さまざまなポイントを考慮したテンプレートを選ぶのが良いだろう。
(4)製造業に合わせた就業規則
業種によって労働条件や就業環境に特性がある。そのため、就業規則の整備に際しては、テンプレートをそのまま使用するのではなく、テンプレートをベースにして製造業の業種特性を加味したカスタマイズをしたほうが良い。
・労働事故に対する備え
製造業は、労働事故の発生率が高い業種である。そのため、自社のリスクを認識し、それを防止するためのルールを明文化することが重要だ。
製造業と一口に言っても、使用する機械や製造工程は企業ごとに異なり、リスクの内容や程度も多様である。そのため、まずは自社の業務において、どのようなリスクが存在するのかを洗い出し、そのリスクを防止するための行動や禁止事項を明記する必要がある。
また、現場の管理者が口頭で注意を促しても従業員の意識が高まりにくい。就業規則にリスク防止のルールを明記すれば、従業員の安全意識を向上させる効果が期待できる。
製造業においては、わずかな不注意が重大な事故につながる可能性があるため、就業規則における労働災害(労災)事故防止に関する規定が欠かせない項目なのである。
・交替勤務や深夜勤務
製造業では交替勤務や深夜勤務が行われる場合も多く、これらに関する規定をより詳細に定めることが重要だ。これらの規定は、絶対的記載事項に該当するため、明確に規定する必要がある。
また、残業や休日出勤の取り扱いを明文化することについても注意したい。さらに、交替勤務を導入する場合、「シフトによる」などのあいまいな記載でなく、各勤務の始業・終業時刻、シフトの組み合わせルール、シフト表作成の手続きと時期などを詳細に定めなければならない。
また、変形労働時間制を採用する場合には、変形期間の総労働時間、各日・各週の労働時間、変形期間の起算日などの明示が必要である。
・安全衛生
製造業では労働事故を防ぐための安全衛生規定も必要になる。これは相対的必要事項であり、定めがある場合には記載する必要があるものだ。
企業には労災の発生を防止する安全配慮義務があり、万が一、労災が発生した場合には、被災労働者への補償や、死亡・休業の報告を労働基準監督署に提出する義務が発生する。
製造業ナレッジリスト
- 【労務担当者向け】製造業の長時間労働の課題に取り組むための5つのFAQ(2025/11/20)
- 【人事労務担当者向け】製造業の人材確保の課題を解決できる5つのFAQ(2025/11/13)
- 【労務担当者向け】製造業の勤怠管理の課題を解決できる5つのFAQ(2025/11/6)
- 製造現場で働き方改革を実現するための3つのポイントを紹介!(2025/10/22)
- 製造業で重要視されるコンプライアンスのポイントとは? 4つの対策を解説(2025/10/15)
- 製造業はなぜ残業が多いのか? 労働時間が多くなる理由と対策を紹介(2025/10/8)
- 製造業で深刻化する人材確保問題の原因と解決策を徹底解説!(2025/10/1)
- 製造現場のDXが重要な理由とは? メリットとおすすめツールも紹介(2025/9/24)
- 製造業の就業規則は業種特性を考慮しよう! 就業規則の作成ポイントを解説(2025/9/10)
- 人材確保につながる製造業の福利厚生とは? 導入のメリットと成功例を解説(2025/9/3)
- 製造業でのOJT活用術! 人材育成におけるメリット・デメリットを解説(2025/8/27)
- 製造業の離職率はどのくらい? 離職率が高まる原因や改善方法も解説(2025/8/20)
- 工場の勤怠管理における課題とは? システム導入のメリットや選定方法も紹介(2025/8/6)
大幅に効率化!
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!

