製造業で深刻化する人材確保問題の原因と解決策を徹底解説!
2025/10/1
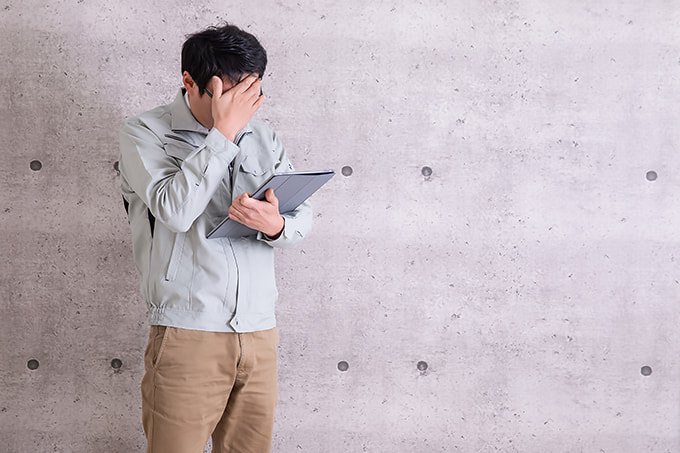
日本の製造業では、長年にわたり人材の確保が重要な経営課題とされてきた。近年、求人を出しても応募が少なく、現場が慢性的な人手不足に陥るケースが急増している。
そのため、生産性の維持どころか、日常業務の遂行にも支障をきたすようになり、多くの企業が深刻な課題として向き合っている。本記事では、製造業における人材不足の実態とその原因を整理した上で、現場が取るべき4つの具体的な解決策について詳しく解説する。
(1)製造業における人材確保の実態
製造業では近年、人材確保が難航している。特に中小企業では、人材の流出や応募者の減少が止まらず、欠員が埋まらないまま操業を続けるケースが目立っている。
さらに、少子高齢化や労働意識の変化といった社会的背景も相まって、製造現場における人材の確保は年々難しくなっている。ここでは、製造業における人材確保の実態について解説する。
・2025年3月の有効求人倍率は1.26倍
厚生労働省の発表によれば、2025年3月時点の全業種における有効求人倍率は1.26倍となっており、求職者1人に対して1件以上の求人がある状態が続いている。これに対し、製造業を含む生産工程従事者に絞ると有効求人倍率は1.59倍に上昇、全体の平均を大きく上回る数値になっている。
このデータからも分かるように、製造業は他業種と比べて、人材確保が難しい状況にある。特に、現場作業や技能職においては、需要が供給を大きく上回っているため、慢性的な人手不足が続いている。
・技能人材の不足が深刻
同じく厚生労働省のデータによると、製造業の中でも特に技能を必要とする職種における人材不足が深刻である。
例えば、製造技術者(開発)の有効求人倍率は2.08倍となっており、求職者の2倍以上の求人が存在している。その上、機械整備・修理従事者に至っては、有効求人倍率が4.06倍と極めて高く、必要とされる人材がほとんど確保できていない状態である。
このように、特定の技能や知識を必要とする職種ほど深刻な人手不足に直面しており、事業継続に大きな影響を及ぼしている。
(2)製造業で人材確保が難しくなる5つの理由
製造業が人材を確保しにくくなっている要因は一つではない。複数の要因が複雑に絡み合い、余計に深刻化している。ここでは、こうした状況を招いている5つの理由について詳しく解説する。
・少子高齢化が進み労働人口が減少
日本の少子高齢化は年々進行しているため、労働市場全体の人手不足が深刻である。総務省によると、2050年には日本の労働人口は5,275万人まで減少すると推計されている。これは2021年からおよそ29.2%もの減少に相当し、今後も働き手の確保が極めて難しくなる見込みである。これは製造業においても例外ではなく、今後ますます労働力が確保しづらくなると予想されている。
・働き盛り世代における後継者不足
後継者不足問題も人材確保が困難になっている要因の一つである。帝国データバンクの調査によれば、国内企業のうち52.1%が後継者不在の状態にあるとされる。特に、製造業では技能やノウハウを持つ人材が高齢化している一方で、その技術を引き継ぐ若手が現れていないのが現状である。
2024年版の中小企業白書やものづくり白書でも、経営者の高齢化と承継問題が事業継続に直結するリスクとして指摘されている。つまり、後継者が育たなければ、現場の技能継承もままならず、人材確保の障壁がさらに高くなるのである。
・製造業の「3K」のイメージを払拭できていない
製造業が敬遠される理由の一つに、いわゆる「3K」と呼ばれる負のイメージがある。3Kとは、「きつい」「汚い」「危険」を指す。この印象が若者や求職者の中に根強く残っているため、業界全体の魅力を損なってしまっている。実際には、設備の近代化や作業の自動化が進んでいるものの、イメージの払拭には至っていない。
・若年層や女性就業者の製造業離れ
製造業における若年層や女性の就業者数は、長期的に減少傾向にある。特に若年層の割合は縮小しており、女性の就業者数も他産業と比較して低水準で推移している。こうした傾向の背景には、少子高齢化に加え、ワーク・ライフ・バランスを重視する価値観の浸透や、製造業に対する重労働・交替制勤務といったイメージが影響していると考えられる。
近年では「働きやすさ」や「柔軟な働き方」が就職先選びの重要な要素となっており、これらの条件が整っていない製造業は、若年層や女性から敬遠される傾向にある。
・製造現場における教育体制
人材育成の現場でも、製造業は大きな課題を抱えている。なぜなら、長年現場を支えてきたベテラン技能者の退職が相次ぎ、指導できる人材が不足しているからである。
その結果、新人や若手が十分な教育を受けられず、現場への定着率も下がっている。教育体制がぜい弱なままでは、採用した人材も早期離職してしまう可能性が高まるため、早急に人材確保対策を実施する必要がある。
(3)製造業の人手不足を解消する4つの対策
製造業における人手不足を解決するには、従来の採用活動だけでは限界がある。そのため、企業はこれまでとは異なる視点からの対策を行わなければならない。
ここでは、実際に効果が期待されている4つの対策について解説する。
・外国人材の積極的な採用
日本国内における外国人労働者の数は年々増加している。内閣府の令和6年度年次経済財政報告によると2023年10月時点で外国人労働者は約205万人に達した。これは少子高齢化によって減少する日本人労働者の代替として、外国人材への依存度が高まっていることを示している。
特に製造業では、技術習得を希望する外国人技能実習生の受け入れが進んでおり、一定の戦力として期待されている。このように、多様な文化や価値観を受け入れる体制を整えることが、製造業の未来を担うカギになるのである。
・ITを活用した業務効率の改善
製造現場では、AIやIoTを活用した業務の効率化が急速に進んでいる。これにより、人が担っていた作業の一部を自動化できるため、必要な人員の数を抑えることが可能である。
また、設備の状態監視や遠隔操作といった仕組みにより、従業員の負担を軽減できる点もメリットである。このように、ITの導入は人手不足の根本的な解決策ではないものの、業務の効率化や負担軽減を通じて、間接的にその課題に対応する手段として、多くの企業から注目を集めている。
・人材の育成体制を整える
採用した人材が短期間で離職する背景には、育成体制の不備がある。業務内容や職場環境に対する理解が不十分なまま現場に配属されることで、業務とのギャップが生じ、結果として早期退職につながるケースが少なくない。
そのため、OJTを含む教育プログラムの再設計や、キャリアの段階に応じた育成制度の整備が重要である。人材が自身の成長を実感でき、安心して働き続けられる環境を構築することで、現場定着率の向上が期待できる。
・ネガティブイメージの払拭
製造業を「3K産業」として敬遠する傾向は今もなお続いている。こうしたマイナスイメージを払拭するためには、企業側からの積極的な情報発信が重要である。
最近ではSNSや動画メディアを活用した採用マーケティングによって、若年層へのアプローチを行う企業が増えてきた。こうしたイメージの刷新は短期間で実現できるものではないが、長期的な人材確保の基盤を築く上で有効な方法である。
(4)まとめ
製造業における人手不足の解消には、多角的な視点での対策が求められる。中でも、外国人材の採用やITの導入は、労働力不足への対応策として積極的に取り入れられている。
育成体制の強化やイメージ戦略の見直しも、長期的な人材の定着と確保に良い影響を与えると言える。このように、いずれの施策も一過性のものではなく、継続的な改善と実践が求められる。
つまり、変化の時代を生き抜くためには、企業が率先して柔軟な取り組みを進めていく姿勢が重要である。
製造業ナレッジリスト
- 【労務担当者向け】製造業の長時間労働の課題に取り組むための5つのFAQ(2025/11/20)
- 【人事労務担当者向け】製造業の人材確保の課題を解決できる5つのFAQ(2025/11/13)
- 【労務担当者向け】製造業の勤怠管理の課題を解決できる5つのFAQ(2025/11/6)
- 製造現場で働き方改革を実現するための3つのポイントを紹介!(2025/10/22)
- 製造業で重要視されるコンプライアンスのポイントとは? 4つの対策を解説(2025/10/15)
- 製造業はなぜ残業が多いのか? 労働時間が多くなる理由と対策を紹介(2025/10/8)
- 製造業で深刻化する人材確保問題の原因と解決策を徹底解説!(2025/10/1)
- 製造現場のDXが重要な理由とは? メリットとおすすめツールも紹介(2025/9/24)
- 製造業の就業規則は業種特性を考慮しよう! 就業規則の作成ポイントを解説(2025/9/10)
- 人材確保につながる製造業の福利厚生とは? 導入のメリットと成功例を解説(2025/9/3)
- 製造業でのOJT活用術! 人材育成におけるメリット・デメリットを解説(2025/8/27)
- 製造業の離職率はどのくらい? 離職率が高まる原因や改善方法も解説(2025/8/20)
- 工場の勤怠管理における課題とは? システム導入のメリットや選定方法も紹介(2025/8/6)
大幅に効率化!
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!

