【2025年度】人事労務に関連する主な法改正をまとめて紹介!
2025/3/19
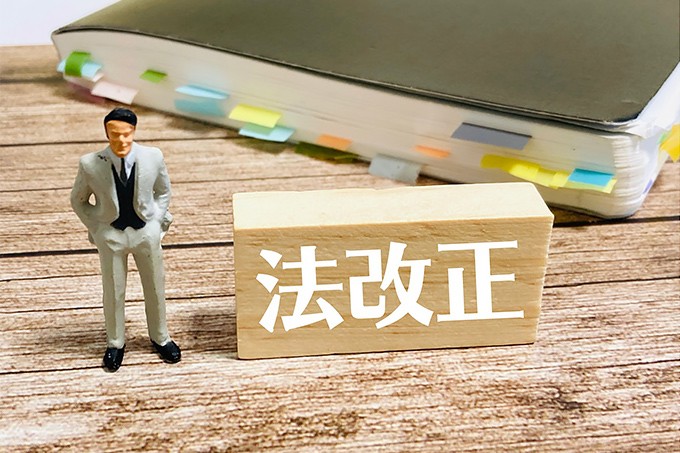
2025年度における人事労務関連の法改正は、雇用保険法、育児・介護休業法などで実施を予定している。これらの改正は、人事労務業務や従業員の働き方などに影響を及ぼす。そのため、人事労務担当者は法改正の内容を正確に把握し、それに対する準備をする必要がある。本稿では、2025年度の主な法改正について、まとめて紹介する。
(1)【2025年4月1日】65歳までの雇用確保措置を完全義務化
2025年3月31日をもって、高年齢者雇用安定法における65歳までの雇用確保措置の経過措置が終了する。この経過措置は、2013年施行の改正で、雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることを義務づけたが、新たな制度への対応、労使協定の調整、年金受給開始年齢との調整が必要なことから定められた。
経過措置が終了したことで、すべての企業は65歳までの雇用を確保するために、「定年制の廃止」「65歳までの定年の引き上げ」「希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じる必要がある。
(2)【2025年4月1日】育児・介護休業法等の改正
2025年4月1日から、育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正が施行される。主な改正点として、子の看護休暇の見直しや所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大、育児休業の取得状況の公表の義務化などが挙げられる。育児休業の取得状況の公表義務は、これまで従業員数1,000人超が対象だったが、この改正で従業員数300人を超える企業に適用されるようになる。
(3)【2025年4月1日】雇用保険法等の改正
2025年4月1日から、雇用保険法と子ども・子育て支援法の改正が施行される。主な改正点として、自己都合退職者の給付制限の見直しや育児を支えるための給付の創設が挙げられる。
自己都合退職者の給付制限の見直しは、これまで、失業給付の受給までに待機満了の翌日から原則2カ月間の給付制限期間があったが、この改正で、給付制限が1カ月に短縮され、自ら教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されるようになる。育児を支えるための給付については、「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の2つが創設される。出生後休業支援給付は、男性の育児休業取得を促進させることが狙い。条件に応じて、育児休業給付と合わせて給付率80%(手取りで10割相当)に引き上げる。
(4)【2025年4月1日】障害者雇用の除外率の引き下げ
2025年4月1日から、障害者雇用の除外率が引き下げられる。除外率は、特定の業種において障害者の雇用義務を軽減するために規定されたもの。除外率は2004年4月に廃止されたが、経過措置として、除外率設定業種ごとに除外率を設定し、段階的に除外率を引き下げている。
今回は除外率設定業種ごとに、除外率が一律10%引き下げられる。この引き下げにより、該当する業種の企業は、より多くの障害者を雇用する義務が生じる。
(5)【2025年10月1日】育児・介護休業法の追加改正
2025年10月1日から、育児・介護休業法の追加改正が施行される。これにより、柔軟な働き方を実現するための措置が義務づけられる。3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、事業主は以下の5つのうちから2つ以上の措置を選択して用意する必要がある。
- ①始業時刻等の変更
- ②テレワーク等(10日以上/月)
- ③保育施設の設置運営等
- ④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- ⑤短時間勤務制度
また、事業主は条件を満たす従業員に対して、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取や配慮することも義務化される。
(6)【2025年10月1日】雇用保険法の追加改正
2025年10月1日から、雇用保険法の追加改正が施行され、「教育訓練休暇給付金」が創設される。この給付金は、教育訓練のために休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えることを目的としている。
法改正ナレッジリスト
- 【2026年4月以降施行】年金制度改正法が成立 年金制度の課題と主な改正内容を解説(2025/6/23)
- 【2025年度】人事労務に関連する主な法改正をまとめて紹介!(2025/3/19)
- 【2025年4月から完全義務化】高年齢者雇用安定法/65歳までの雇用確保措置の経過措置が終了に(2025/1/15)
- 【2025年1月施行】健康診断結果報告等の電子申請が義務化に(2025/1/8)
- 【2024年12月施行】改正された確定給付企業年金制度 iDeCoは何が変わったか?(2024/12/25)
- 障害者雇用促進法改正による2025年4月の施行内容とは?(2024/12/11)
- 【2024年~2028年施行】雇用保険法等改正による変更点(2024/12/4)
- 【2025年4月から施行】育児・介護休業法等改正による変更点(2024/11/27)
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!
