【2024年~2028年施行】雇用保険法等改正による変更点
2024/12/4
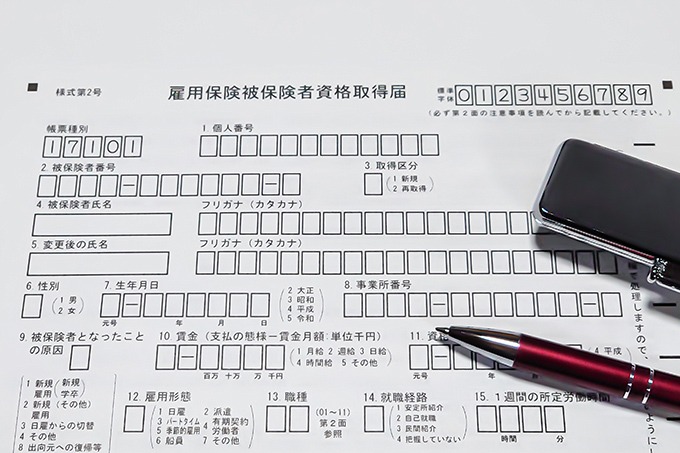
(1)雇用保険法とは
雇用保険法は1974年12月に成立。この法律は、失業保険法(1947年制定)に代わるもので、労働者の生活と雇用の安定を図るために制定された。雇用保険法には「基本手当」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」「育児休業給付」といった給付が規定されている。雇用保険法は労働市場の変化や社会的ニーズに対応するために定期的に見直しが行われ、直近では2024年5月に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、2024年から2028年にかけて順次施行される。
- ※参考:[厚生労働省]雇用保険制度
(2)規定されている給付
雇用保険法では、以下の給付が規定されている。
・基本手当
基本手当は、失業した労働者に対して支給される給付。いわゆる「失業手当」のこと。これは、失業中の生活を支えるための重要な制度であり、失業者が次の職を見つけるまでの間、一定の収入を確保することを目的としている。基本手当の支給額は、離職前の賃金日額にもとづいて算出され、賃金日額の約50%から80%の範囲(60歳から64歳については45%から80%)で支給される。支給期間は、被保険者期間や年齢、離職理由等によって異なるが、90日から360日の範囲で決められる。
・就職促進給付
就職促進給付は、失業者が早期に再就職することを支援するための給付のこと。この給付には、「再就職手当」「就業促進定着手当」などが含まれる。「再就職手当」は、基本手当の支給残日数が一定以上残っている状態で早期に再就職した場合に支給されるもので、支給額は基本手当の支給残日数に応じて決定される。「就業促進定着手当」は、再就職手当の支給を受けた人が、再就職後に一定期間継続して就業し、離職前の賃金日額よりも低下している場合に支給される。
・教育訓練給付
教育訓練給付は、労働者が職業に関する教育訓練を受ける際に支給される給付のこと。この給付には、「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3種類がある。「一般教育訓練給付金」は、労働者が一般的な職業訓練を受ける際に支給されるもので、支給額は受講費用の20%(上限10万円)。「特定一般教育訓練給付金」は、労働者の速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象で、受講費用の40%(上限20万円)が支給され、さらに、資格を取得し、訓練修了後、1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合には、受講費用の10%(上限5万円)が追加になる。
「専門実践教育訓練給付金」は、より専門的な職業訓練を受ける際に支給されるもので、支給額は受講費用の50%(年間上限40万円)。資格を取得し、訓練修了後、1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給される。
・雇用継続給付
雇用継続給付は、高年齢者や介護を行う労働者が、引き続き雇用されることを支援するための給付のこと。この給付には、「高年齢雇用継続給付」と「介護休業給付」の2種類がある。「高年齢雇用継続給付」は、60歳以上の労働者が引き続き雇用される場合に支給されるもので、賃金が60歳到達時点に比べて低下した場合に、その差額の一部が支給される。「介護休業給付」は、介護休業を取得した労働者に対して支給されるもので、休業開始時の賃金日額の67%が支給される。なお、「高年齢雇用継続給付」は2020年に廃止が決定し、2025年度から段階的に給付率が引き下げられる。
・育児休業給付
「育児休業給付」は、育児休業を取得した労働者に対して支給される給付のこと。この給付は、育児休業中の収入を補填し、育児と仕事の両立を支援することを目的としている。「育児休業給付」の支給額は、休業開始時の賃金日額の67%であり、育児休業の開始から180日目以降は50%に引き下げられる。支給期間は、原則として子が1歳に達するまでであるが、一定の条件を満たす場合には最長で2歳まで延長することができる。
(3)今回の改正の目的
今回の改正の目的は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築と、「人への投資」の強化を図ること。現代の労働市場では、パートタイムやフリーランスなど、多様な働き方が増加し、従来の雇用保険制度ではカバーしきれない労働者が増えている。週所定労働時間が20時間未満の労働者も含め、より多くの労働者が雇用保険の対象となるようにすることで、セーフティネットを拡充し、すべての労働者が安心して働ける環境を整える必要がある。
また、技術革新や産業構造の変化により、労働者が新たなスキルを習得する必要性が高まっている。教育訓練給付金の拡充や新たなリスキリング支援の導入により、労働者がキャリアアップや再就職を目指す際の経済的負担を軽減し、労働市場での競争力を高めることが求められている。
(4)主な改正内容
主な改正内容は以下のとおり。一部、今回の法改正とは異なる法改正に伴うものも含まれる。
・育児休業給付の国庫負担割合の暫定措置の廃止
育児休業の取得者数の増加等に伴い、育児休業給付の支給額が年々増加。財政基盤を強化するため、育児休業給付の国庫負担割合を、これまで1/80としていた暫定措置を廃止して、本則の1/8に引き上げた。
・介護休業給付の国庫負担割合の暫定措置の継続
介護休業給付の国庫負担割合を1/80とする暫定措置を2026年度末まで継続することとした。
・教育訓練給付の拡充
訓練効果を高めるために教育訓練給付金の給付率の上限を引き上げる。「専門実践教育訓練給付金」は、これまでの70%(本体給付+資格取得等の追加給付)に、受給後に賃金が上昇した場合の追加給付10%を加えた80%が最大給付率になる。「特定一般教育訓練給付金」は、これまでの40%(本体給付)に、資格を取得して就職した場合の追加給付10%が加算される。
・自己都合退職者の給付制限の見直し
正当な理由のない自己都合で退職した労働者は、失業給付の受給までに待機満了の翌日から原則2カ月間の給付制限期間がある。(ハローワークが指示した職業訓練を受講した場合は給付制限が解除)今回の改正で給付制限が1カ月に短縮され、自ら教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除される。
・就業促進給付の見直し
就業促進給付において支給されている「就業手当」「再就職手当」「就業促進定着手当」のうち、受給者数が少ない「就業手当」については廃止。(2022年度実績で就業手当3,486人、再就職手当359,734人、就業促進定着手当92,546人)また、「就業促進定着手当」については人手不足の状況等を考慮して、上限を基本手当の支給残日数の20%相当に引き下げる。
・育児休業給付の保険料率引き上げと弾力的な仕組みの導入
今後の保険財政の悪化に備えて、雇用保険の本則料率を0.4%から0.5%に引き上げ、保険財政の状況に応じて弾力的に調整できる仕組み(※1)にする。当面は0.4%に据え置かれる。
- ※1 前年度の決算を踏まえた該当年度の積立金残高(見込み)と翌年度の収入(見込み)の合計額が、翌年度の支出(見込み)の1.2倍を超える場合は、翌年度の料率を0.4%にすることができる。
・2024年度末までの暫定措置の継続
「雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例」「地域延長給付」は2026年度末まで継続。「教育訓練支援給付金」も2026年度まで継続するが、給付率を基本手当日額の80%から同60%に引き下げる。
・育児を支えるための給付の創設(※2)
「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の2つが創設される。「出生後休業支援給付」は、「共働き・共育て」を念頭に、特に男性の育児休業取得を促進させることが狙い。子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付と合わせて、給付率80%(手取りで10割相当)に引き上げる。
「育児時短就業給付」は、短時間勤務制度(時短勤務)を選択した場合に低下した賃金を補填するための給付。時短勤務中に支払われた賃金の10%が給付される。
・子ども・子育て支援特別会計の創設(※2)
こども・子育て政策の全体像と費用負担を可視化するため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定と労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、子ども・子育て支援特別会計を創設する。
- ※2 2024年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に関連して雇用保険制度が改正される。
・高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ(※3)
これまで上限15%だった給付率が10%に引き下げられる。ただし、2025年3月末までに60歳になった労働者は15%が維持される。
- ※3 2020年の雇用保険法改正に伴う施行。
・教育訓練中の生活を支えるための給付の創設
教育訓練のために休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、新たに「教育訓練休暇給付金」を創設する。教育訓練の休暇が無給で、雇用保険の被保険者期間が5年以上の場合に、失業給付の基本手当と同額が支給される。給付日数は被保険者期間に応じて、90日、120日、150日のいずれか。
労務ナレッジリスト
- 労務管理の基礎知識(2024/8/28)
- ‐労務管理における労働契約とは?(2024/10/9)
- ‐労働条件の明示義務 雇用契約後のトラブルを回避するために(2025/3/26)
- ‐労務管理における入退社手続きとは?(2024/10/16)
- ‐【2024年~2028年施行】雇用保険法等改正による変更点(2024/12/4)
- ‐迫る健康保険証廃止 企業でやるべきことは何なのか?(2024/11/20)
- ‐労務管理における勤怠管理とは?(2024/10/23)
- ‐時間外労働の上限規制とは? 働き方改革で求められる対応策について解説(2026/2/4)
- ‐夜勤の労働時間管理のポイントは? システム導入で期待できる効果も紹介(2025/6/18)
- ‐じわり広がる週休3日制 導入が進む背景とは?(2025/4/2)
- ‐【2025年4月から施行】育児・介護休業法等改正による変更点(2024/11/27)
- ‐労務管理における給与計算とは?(2024/10/30)
- ‐【2025年】「年収の壁」見直しによる年末調整における変更点(2025/11/7)
- ‐【2024年12月施行】改正された確定給付企業年金制度 iDeCoは何が変わったか?(2024/12/25)
- ‐2024年の年末調整における定額減税の注意点(2024/11/6)
- ‐労務管理における安全衛生管理とは?(2024/11/13)
- ‐作業員の労働災害を防ぐ安全教育とは? 安全教育の重要性や効果的な指導方法を解説(2025/9/17)
- ‐労働災害時の対応手順は? 提出書類や発生前に確認しておきたい内容も解説(2025/8/13)
- ‐過去最多の猛威を振るう季節性インフルエンザ 会社や学校の対応は?(2025/1/22)
- ‐【2025年1月施行】健康診断結果報告等の電子申請が義務化に(2025/1/8)
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!
