【2025年4月から施行】育児・介護休業法等改正による変更点
2024/11/27
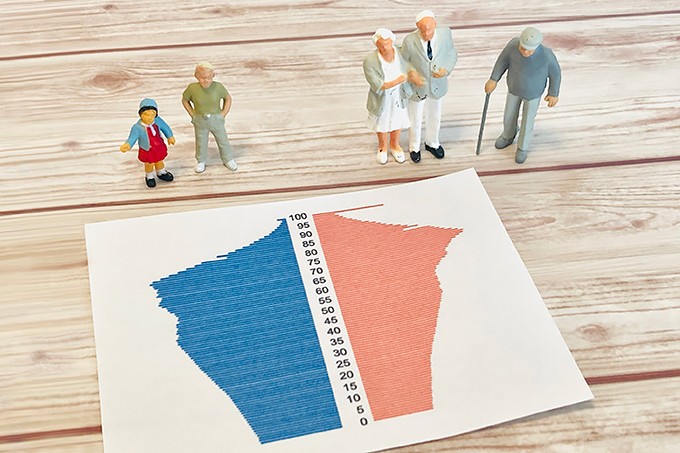
(1)育児・介護休業法とは
育児・介護休業法は、子育てや介護などによって時間的に制約を受ける労働者の仕事と家庭の両立を支援するための法律。「育児休業」「子の看護休暇」「介護休業」「介護休暇」等が規定されている。
子を養育する労働者の雇用継続を促進するため、1991年に、単独の法律として「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が成立。女性の社会進出、核家族化の進行、少子化に伴う労働力不足などを背景に、男女問わず、すべての労働者を対象として、育児休業や短時間勤務等が制度化された。その後、社会の高齢化が進行し、介護に関するニーズが増大。それに伴って、1995年に介護休業等を盛り込んだ「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(現在は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」(育児・介護休業法)として改正された。
(2)規定されている制度
育児・介護休業法では、以下の制度が規定されている。
・育児休業
育児休業とは、労働者が子を出生した後、一定期間、育児に専念するために取得する休業のこと。育児・介護休業法にもとづき、育児休業は原則として子が1歳になるまで取得可能であるが、特定の条件を満たす場合には最長で2歳まで延長することができる。
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されるため、経済的な負担が軽減される。育児休業の取得は、男女問わず可能であり、最近では男性の育児休業取得率も徐々に増加している。育児休業を取得することで、親子の絆を深めるとともに、育児に対する理解と協力を促進することが期待される。
・子の看護休暇
子の看護休暇とは、労働者が病気やケガをした子の看護を行うために取得する休暇のこと。育児・介護休業法にもとづき、小学校就学前の子を持つ労働者は、年5日の看護休暇を取得することができる。対象となる子が2人以上いる場合は、年10日まで取得可能である。
・介護休業
介護休業とは、労働者が家族の介護を行うために取得する休業のこと。育児・介護休業法にもとづき、介護休業は対象家族1人につき通算93日まで取得することができる(3回まで分割可能)。介護休業中は、雇用保険から介護休業給付金が支給されるため、経済的な負担が軽減される。
介護休業の取得は、労働者が家族の介護に専念するための時間を確保し、介護と仕事の両立を支援するもの。介護休業を取得することで、介護者の負担を軽減し、家族の介護に対する理解と協力を促進することが期待される。
・介護休暇
介護休暇とは、労働者が家族の介護を行うために取得する短期の休暇のこと。育児・介護休業法にもとづき、要介護状態にある家族を持つ労働者は、年5日の介護休暇を取得することができる。2人以上の要介護者がいる場合は、年10日まで取得可能。介護休業が長期での介護を想定して利用するのに対して、介護休暇は突発的に休まざるを得ない場合に適している。
(3)育児・介護休業法等の改正の目的
1991年の成立から、育児・介護休業法は改正を重ね、時代の変化に合わせて強化されてきた。直近では2024年5月に改正法案が国会で可決・成立。2025年4月から施行される。この改正では、育児・介護休業法のほか、次世代育成支援対策推進法が改正された。改正の目的は以下のとおり。
・柔軟な働き方の実現
子の年齢に応じた柔軟な働き方を可能にするための措置を拡充する。これにより、育児や介護を行う労働者が仕事と家庭を両立しやすくなる。
・介護離職防止のための支援制度の強化
介護離職を防ぐため、仕事と介護の両立支援制度を強化する。これには、介護期におけるテレワークの導入や、介護休暇の対象者拡大などが含まれる。
(4)2025年4月1日施行の改正内容
・子の看護休暇の見直し《義務:就業規則等の見直し》
対象範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大。取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加される。また、これまで、子の看護休暇の取得の除外条件としていた「週の所定労働日数が2日以下」「継続雇用期間6カ月未満」のうち、「継続雇用期間6カ月未満」については撤廃される。なお、「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に名称が変わる。
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大《義務:就業規則等の見直し》
対象範囲が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大される。
・短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加《選択する場合は就業規則等の見直し》
短時間勤務制度とは、いわゆる「時短勤務」のこと。3歳未満の子を養育している労働者は、一定の条件を満たせば、1日の労働時間を6時間にして働くことができる。ただし、短時間勤務制度の実施が困難な場合は労使協定を締結し、除外規定を設けて、事業主は代替措置を用意しなくてはならない。その代替措置はこれまで「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等」の2つが規定されていたが、3つ目として「テレワーク」が追加される。
・育児のためのテレワーク導入《努力義務:就業規則等の見直し》
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることが、事業主の努力義務になる。
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大《義務》
これまで公表義務の対象となる企業規模は従業員数1,000人超だったが、同300人超になる。
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和《労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し》
これまで除外条件としていた「継続雇用期間6カ月未満」が撤廃され、「週の所定労働日数が2日以下」のみになる。
・介護離職防止のための雇用環境整備《義務》
事業主は以下のいずれかを実施しなければならない。
- ①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- ②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- ③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- ④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等《義務》
介護に直面した旨を申し出た労働者に対して、事業主は介護休業制度や介護両立支援制度などの内容等を周知する必要がある。加えて、同制度の利用意向の確認を個別に行う。また、介護に直面していなくても、労働者が40歳になる年の年度、もしくは40歳になった日の翌日から1年の間に情報の周知を行うことが義務化される。
・介護のためのテレワーク導入《努力義務:就業規則等の見直し》
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにすることが、事業主の努力義務になる。
(5)2025年10月1日施行の改正内容
・柔軟な働き方を実現するための措置等《義務:就業規則等の見直し》
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、事業主は以下の5つのうち、2つ以上の措置を選択して用意する必要がある。(選択に際しては、過半数組合等の意見聴取の機会を設ける)
- ①始業時刻等の変更
- ②テレワーク等(10日以上/月)
- ③保育施設の設置運営等
- ④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- ⑤短時間勤務制度
選択した措置の内容等を適切な時期(労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間)に、周知し、利用意向を確認しなくてはならない。労働者は、事業主が用意した中から1つを選んで利用する。
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮《義務》
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければならない。
- ①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- ②勤務地(就業の場所)
- ③両立支援制度等の利用期間
- ④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
聴取内容をもとに、事業主は、自社の状況に応じて配慮する義務を負う。
労務ナレッジリスト
- 労務管理の基礎知識(2024/8/28)
- ‐労務管理における労働契約とは?(2024/10/9)
- ‐労働条件の明示義務 雇用契約後のトラブルを回避するために(2025/3/26)
- ‐労務管理における入退社手続きとは?(2024/10/16)
- ‐【2024年~2028年施行】雇用保険法等改正による変更点(2024/12/4)
- ‐迫る健康保険証廃止 企業でやるべきことは何なのか?(2024/11/20)
- ‐労務管理における勤怠管理とは?(2024/10/23)
- ‐時間外労働の上限規制とは? 働き方改革で求められる対応策について解説(2026/2/4)
- ‐夜勤の労働時間管理のポイントは? システム導入で期待できる効果も紹介(2025/6/18)
- ‐じわり広がる週休3日制 導入が進む背景とは?(2025/4/2)
- ‐【2025年4月から施行】育児・介護休業法等改正による変更点(2024/11/27)
- ‐労務管理における給与計算とは?(2024/10/30)
- ‐【2025年】「年収の壁」見直しによる年末調整における変更点(2025/11/7)
- ‐【2024年12月施行】改正された確定給付企業年金制度 iDeCoは何が変わったか?(2024/12/25)
- ‐2024年の年末調整における定額減税の注意点(2024/11/6)
- ‐労務管理における安全衛生管理とは?(2024/11/13)
- ‐作業員の労働災害を防ぐ安全教育とは? 安全教育の重要性や効果的な指導方法を解説(2025/9/17)
- ‐労働災害時の対応手順は? 提出書類や発生前に確認しておきたい内容も解説(2025/8/13)
- ‐過去最多の猛威を振るう季節性インフルエンザ 会社や学校の対応は?(2025/1/22)
- ‐【2025年1月施行】健康診断結果報告等の電子申請が義務化に(2025/1/8)
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!
