じわり広がる週休3日制 導入が進む背景とは?
2025/4/2

昨年12月、東京都の小池百合子知事が、2025年度から週休3日制を導入する方針を示した。フレックスタイム制を活用し、希望する職員が選択する仕組みを想定している。これは、職員に対する子育てと仕事の両立のための新たな支援策として位置づけている。
ほかの自治体では、2024年4月に茨城県、同年6月に千葉県では導入済み。大阪府などでも2025年1月から開始された。検討中の自治体も多く、続々と導入に広がりが見られる。これまで、一部の民間企業で導入されてきた週休3日制だが、厚生労働省の就労条件総合調査(2023年)によれば、「完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度」(月1回以上週休3日制、3勤3休、3勤4休等)を導入している企業の割合はわずか7.5%。自治体での動きは果たして、週休3日制の普及に影響を与えるのだろうか?
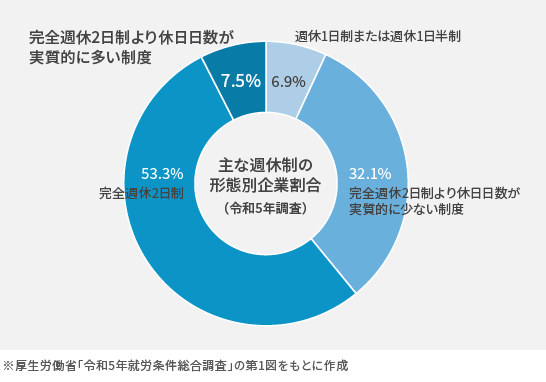
(1)週休3日制とは
週休3日制とは、1週間のうち3日間を休日とする制度のこと。従来の週休2日制に比べて、労働者の働き方の柔軟性を高め、育児、介護、治療と仕事の両立、学び直し、余暇の充実、地域貢献など、働く人々のワーク・ライフ・バランスを向上させる狙いがある。この制度は、大きく3つのタイプに分類できる。
| タイプ | 内容 |
|---|---|
①労働時間・給与ともに維持 |
週休2日制と同じ総労働時間を維持しながら、1日の労働時間を増やす。例えば、1日10時間労働を4日間行うことで、週40時間の労働となる。 |
②労働時間・給与ともに削減 |
労働時間が減る分、給与も減額される。例えば、週32時間労働に対して給与が80%に減額される。 |
③労働時間削減、給与維持 |
週休2日制と同じ給与を維持しながら、労働時間を減らす。例えば、1日8時間労働を4日間行うことで、週32時間の労働となるが、給与は維持される。労働者は給与を減らさずに休暇を増やすことができるが、企業側は生産性の向上を求める。 |
日本の導入タイプは①か②が一般的。自治体で導入が進む週休3日制もこれらに該当する。
その一方で③は海外で導入されることが多い。海外で週休3日制が注目されたきっかけといえば、アイスランドの実証実験が大きい。アイスランドでは、2015年から2019年にかけて、給与を維持しながら週の労働時間を40時間から35時間または36時間に削減する大規模な実証実験を行った。実験の結果、多くの職場で生産性の向上が確認され、加えて、労働者の幸福度や健康状態の改善も見られたという。厳密にいうと、週休を3日にするというよりも、労働時間を減らすことを目的とした実証実験なのだが、この成功事例が他国にも影響を与え、週休3日制の導入を検討する動きにつながっていった。
(2)週休3日制を導入するメリット
週休3日制を導入するメリットとして、主に以下の3つが挙げられる。
・ワーク・ライフ・バランスの向上
週休3日制は、労働者が仕事とプライベートのバランスを取りやすくする。特に育児や介護を行う労働者にとって、追加の休暇は大きな助けとなる。
・生産性の向上
休暇が増えることで、労働者はリフレッシュし、集中力や効率が向上する可能性がある。これにより、限られた時間内での生産性が向上し、企業全体の業績にも良い影響を与える。
・人材確保と離職率の低下
週休3日制を導入することで、企業は他社との差別化を図り、優秀な人材を確保しやすくなる。また、労働者の満足度が向上し、離職率の低下にもつながる。
(3)週休3日制のデメリット
週休3日制の導入により、企業や労働者は、前項のようなメリットを享受できる一方で、以下のようなデメリットも懸念される。
(4)多様な働き方の拡大
週休3日制の導入は、労働者の多様な働き方の一環として位置づけられる。多様な働き方の推進は、「働き方改革」の目的のひとつ、「働く人のニーズの多様化」への対応でもある。これにより、企業は様々な働き方を提供することが求められている。週休3日制は、2021年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針2021)において選択的週休3日制の導入・推進が盛り込まれている。
- ※参考:[用語集]働き方改革
- ※参考:[内閣府]経済財政運営と改革の基本方針2021
週休3日制のほか、多様な働き方を実現するための主な仕組みや制度は以下のとおり。
・リモートワーク
ICTを活用して在宅勤務やサテライトオフィス勤務を行うことで、通勤の負担を軽減し、仕事とプライベートの両立を図る。
・フレックスタイム制
コアタイムとフレキシブルタイムを設定し、労働者が自由に出退勤時間を選べるようにする。
・短時間勤務制度
育児や介護を行う労働者向けに、フルタイムよりも短い勤務時間でを設定する制度。
・副業・兼業
労働者が本業以外に副業や兼業を行うことで、所得増やスキルアップを図る。
・ジョブ型雇用
職務の専門性を重視した雇用形態のため、労働者が自分の得意分野で能力を発揮しやすくなり、生産性やモチベーションの向上が期待される。
これらの仕組みや制度は、労働者の多様なニーズに応えるためのものであり、企業にとっても生産性向上や人材確保の手段となる。
労務ナレッジリスト
- 労務管理の基礎知識(2024/8/28)
- ‐労務管理における労働契約とは?(2024/10/9)
- ‐労働条件の明示義務 雇用契約後のトラブルを回避するために(2025/3/26)
- ‐労務管理における入退社手続きとは?(2024/10/16)
- ‐【2024年~2028年施行】雇用保険法等改正による変更点(2024/12/4)
- ‐迫る健康保険証廃止 企業でやるべきことは何なのか?(2024/11/20)
- ‐労務管理における勤怠管理とは?(2024/10/23)
- ‐夜勤の労働時間管理のポイントは? システム導入で期待できる効果も紹介(2025/6/18)
- ‐じわり広がる週休3日制 導入が進む背景とは?(2025/4/2)
- ‐【2025年4月から施行】育児・介護休業法等改正による変更点(2024/11/27)
- ‐労務管理における給与計算とは?(2024/10/30)
- ‐【2025年】「年収の壁」見直しによる年末調整における変更点(2025/11/7)
- ‐【2024年12月施行】改正された確定給付企業年金制度 iDeCoは何が変わったか?(2024/12/25)
- ‐2024年の年末調整における定額減税の注意点(2024/11/6)
- ‐労務管理における安全衛生管理とは?(2024/11/13)
- ‐作業員の労働災害を防ぐ安全教育とは? 安全教育の重要性や効果的な指導方法を解説(2025/9/17)
- ‐労働災害時の対応手順は? 提出書類や発生前に確認しておきたい内容も解説(2025/8/13)
- ‐過去最多の猛威を振るう季節性インフルエンザ 会社や学校の対応は?(2025/1/22)
- ‐【2025年1月施行】健康診断結果報告等の電子申請が義務化に(2025/1/8)
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!
