【2025年】「年収の壁」見直しによる年末調整における変更点
2025/11/7

年末調整は、給与所得者にとって1年間の所得税を確定する重要な手続きであり、企業の労務・経理担当者にとっても慎重な対応が求められる業務である。
2025年(令和7年)の年末調整では、主に「年収の壁」対策を目的とした令和7年度税制改正が適用される。この改正により、基礎控除、給与所得控除、扶養控除などが大きく見直され、年末調整の実務にも大きな影響を及ぼす内容になっている。
本記事では、2025年分の年末調整における主な改正のポイントを整理し、実務対応における具体的な注意点を解説する。
(1)そもそも控除とは
税制における「控除」とは、課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことを指す。日本の所得税制度は、単に収入の全体額に対して課税するのではなく、「収入」から「必要経費」や各種「控除」を差し引いて算出される「課税所得」に対して課税される仕組みを採用している。この控除の金額が大きくなるほど、課税所得は減少し、結果として納税者が負担する所得税や住民税の額が軽減されることになる。
所得税法上の控除は、大きく2つに分類される。
①所得控除
所得控除は、納税者本人の個人的な事情(扶養している家族の有無、生命保険料や社会保険料の支払い、病気や災害による支出など)を考慮し、公平な課税を実現するために所得全体から差し引かれるものである。所得控除には、すべての人に適用される基礎控除をはじめ、特定の条件を満たす場合に適用される扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除などが存在する。年末調整では、この所得控除のうち、生命保険料控除など、従業員からの申告にもとづいて適用される控除の計算が主な業務になる。
2025年の税制改正で注目される基礎控除や、新たに創設された特定親族特別控除は、この所得控除に分類される。
- ※参考:[国税庁]所得控除のあらまし
②給与所得控除
給与所得控除は、給与所得者特有の控除のこと。会社員や公務員などの給与所得者は、事業主とは異なり、仕事で発生した経費を個別に計上することが難しい。そこで、給与所得控除は、「必要経費の概算額」として、収入金額に応じて一律に給与収入から差し引かれる。
- ※参考:[国税庁]給与所得控除
所得税の計算上、「給与収入」からこの「給与所得控除」を差し引いたものが「給与所得」となり、さらにここから各種「所得控除」を差し引いた残りが「課税所得」になる。
(2)2025年の年末調整の主な変更点
・基礎控除と給与所得控除の見直し
所得税の非課税ライン(いわゆる103万円の壁)の引き上げなどを目的として、基礎控除および給与所得控除が見直された。
基礎控除の変更内容は以下のとおり。
| 合計所得⾦額 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 (2027年分以後は58万円) |
|
| 336万円超489万円以下 | 68万円 (2027年分以後は58万円) |
|
| 489万円超655万円以下 | 63万円 (2027年分以後は58万円) |
|
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | |
給与所得控除については、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられた。これらの改正(基礎控除の最大95万円と給与所得控除の65万円)により、給与収入が160万円までで、ほかに所得がなければ、所得税・復興特別所得税が非課税になるなど、納税者の税負担が大きく軽減される。
・扶養控除や配偶者控除などの所得要件の緩和
各種控除の適用判定に用いる扶養親族・配偶者等の合計所得金額の要件を緩和。控除対象となる扶養親族、同一生計配偶者、控除対象配偶者などの合計所得金額の要件が、従来の「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられる。 パートやアルバイトの収入のみの場合、年収103万円超123万円以下の親族についても、新たに扶養親族や控除対象配偶者となる可能性がある。
・特定親族特別控除の創設
「年収の壁」を超えて働きたい学生などがいる世帯の税負担を軽減するため、特定親族特別控除という新たな所得控除が創設された。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額※) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
- ※特定支出控除の適用がある場合は金額が異なる
- ※参考:[国税庁]特定親族特別控除
基礎控除と給与所得控除の見直しや扶養控除の所得要件の緩和により、特定扶養控除の適用要件は年103万円から123万円に引き上げられている。それに加えて、特定親族特別控除の創設により、学生などが年123万円を超えて働く場合にも、世帯の税負担を軽減できるようになった。
納税者に、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの目安で123万円超188万円以下)の年齢19歳以上23歳未満の特定親族がいる場合に、特定親族特別控除が適用される。特定親族の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が適用される。
例えば、合計所得金額が58万円超85万円以下(給与収入のみの目安で123万円超150万円以下)の場合は、最高額の63万円が納税者の所得から控除される。これにより、特定親族のアルバイト収入が年123万円(合計所得金額58万円)を超えても、年188万円以下までの範囲で、世帯全体で一定の税負担軽減を受けられるようになる。
(3)年末調整の実務における対応と注意点
2025年の改正は、年末調整業務に直接影響を及ぼす。特に以下の点に注意が必要である。
・申告書様式の変更
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が統合され、新たな様式になる。従業員への配布、回収、確認作業において、新しい申告書様式を使用し、特に「特定親族特別控除」の記載漏れや誤記がないかを注意深く確認する必要がある。
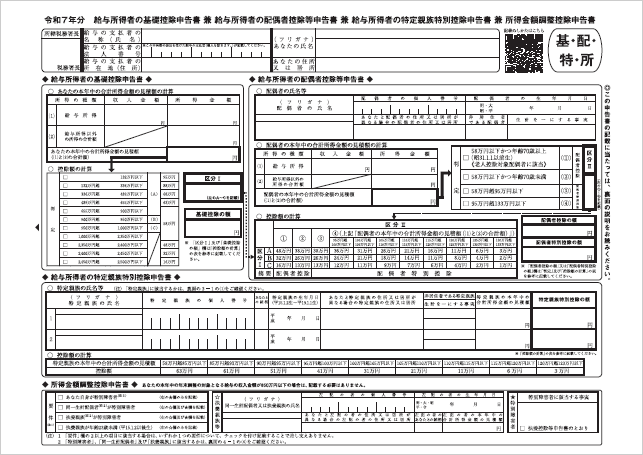
・従業員への周知と申告内容の確認
所得要件の緩和や新控除の創設により、控除の対象となる従業員が増加する可能性がある。申告書の記入にあたり、従業員に対して、扶養親族や配偶者等の合計所得金額要件が58万円以下に緩和された点や特定親族特別控除について周知を徹底し、申告の「漏れ」がないように促す必要がある。
・給与計算システムの改修
基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除などの改正に伴い、年末調整の計算ロジックを変更する必要がある。利用している給与計算ソフトや年末調整システムが、改正後の控除額、所得要件、計算方法に正確に対応しているか、ベンダーと連携して早急に確認・アップデートを行う必要がある。
労務ナレッジリスト
- 労務管理の基礎知識(2024/8/28)
- ‐労務管理における労働契約とは?(2024/10/9)
- ‐労働条件の明示義務 雇用契約後のトラブルを回避するために(2025/3/26)
- ‐労務管理における入退社手続きとは?(2024/10/16)
- ‐【2024年~2028年施行】雇用保険法等改正による変更点(2024/12/4)
- ‐迫る健康保険証廃止 企業でやるべきことは何なのか?(2024/11/20)
- ‐労務管理における勤怠管理とは?(2024/10/23)
- ‐時間外労働の上限規制とは? 働き方改革で求められる対応策について解説(2026/2/4)
- ‐夜勤の労働時間管理のポイントは? システム導入で期待できる効果も紹介(2025/6/18)
- ‐じわり広がる週休3日制 導入が進む背景とは?(2025/4/2)
- ‐【2025年4月から施行】育児・介護休業法等改正による変更点(2024/11/27)
- ‐労務管理における給与計算とは?(2024/10/30)
- ‐【2025年】「年収の壁」見直しによる年末調整における変更点(2025/11/7)
- ‐【2024年12月施行】改正された確定給付企業年金制度 iDeCoは何が変わったか?(2024/12/25)
- ‐2024年の年末調整における定額減税の注意点(2024/11/6)
- ‐労務管理における安全衛生管理とは?(2024/11/13)
- ‐作業員の労働災害を防ぐ安全教育とは? 安全教育の重要性や効果的な指導方法を解説(2025/9/17)
- ‐労働災害時の対応手順は? 提出書類や発生前に確認しておきたい内容も解説(2025/8/13)
- ‐過去最多の猛威を振るう季節性インフルエンザ 会社や学校の対応は?(2025/1/22)
- ‐【2025年1月施行】健康診断結果報告等の電子申請が義務化に(2025/1/8)
カスタマイズできる
ProSTAFFクラウド
-
ProSTAFFクラウドの資料を
いますぐダウンロード! -
サービスデモのご依頼や
ご質問についてはお気軽に!
